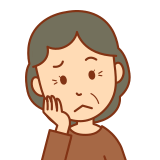
最近、寝付きが悪くて困っています。睡眠薬を使いたいんですが。

すぐに薬に頼ることはお勧めしません。まずは生活改善でできることから始めましょう。
内科の外来をしていると、睡眠障害で受診する人が結構います。本来なら、精神科や心療内科で診断・治療するのが良いと思うのですが、それらの科は敷居が高いのでしょうか。内科にやってくるのです。また、高血圧や糖尿病など、他の病気で通院している人が「近ごろ、なかなか眠されないんです」と訴えてくることもあります。
ところで、不眠・睡眠障害と一口で言っても、いくつかのパターンに分けられます。
①横になってもなかなか眠れない『入眠障害型』
②夜間に何度も目が覚めてしまう『途中覚醒型』
③早くに目が覚めてしまう『早朝覚醒型』
この3つが主なパターンです。人によっては①と②の両方であったり、①と③であったりする場合もあります。
これらの患者さんの多くは、薬によって何とかしてほしいという希望を持っています。いわゆる『睡眠薬』です。
(時々、『睡眠薬』ではなく『安定剤』を欲しいという人がいますが、この両者は基本的にほぼ同じものです)
以前から使われてきた睡眠薬は、脳の活動を鎮静化させるGABA中枢という所に作用して、脳全体の活動を抑え込んでしまう薬です。脳の活動を鎮静化することで、眠くなったり気分が落ち着いたりするのです。「眠りに就く」というよりも、「ゆっくり気を失う」という表現が近いかもしれません。こうした従来の睡眠薬には問題点があり、昼間にも頭がボーとしたり、高齢者の認知症が悪化する原因にもなると言われています。また、「薬がないと眠れない」という依存状態を起こすこともあります。以前の物に比べると依存症になりにくいと言われていますが、いったん飲み始めると止められない方が多いです。
中には、なかなか眠れないからと睡眠薬を2種類、3種類と飲んでいる人もいます。こうした薬剤(ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系と呼ばれる薬剤)を飲み続けなくてはならない状況は健全とは言えません。
最近の研究で、人間の睡眠がどうやって起こるのか、ある程度分かってきました。脳の中には「起きようとする」覚醒系の神経中枢と「眠ろうとする」睡眠系の神経中枢があります。覚醒系の力が強くなると目が覚めて、睡眠系の力が強いと眠くなります。従来の睡眠薬は睡眠系中枢の一種であるGABAという所に作用すると言われています。
また、睡眠に影響するホルモンがあることも分かっています。アデノシンというホルモンは睡眠を誘う作用がありますが、コーヒーなどに含まれるカフェインはこのアデノシンの働きをブロックすることで、眠気を抑える作用があります。
他に睡眠を促すホルモンとしてはメラトニンというものがあります。メラトニンは脳の中で作られるホルモンで、昼間は少なく夜になると増えてきます。目で明るさを感じると分泌が減り、それから約15時間後に分泌がピークになると言われています。ですから、朝に太陽の光を浴びることで、その日の夜はしっかり眠ることができるという仕組みです。寝つきが悪くて困っている方は試してみてください。また、夜に強い光を見ることは、メラトニンの分泌サイクルを狂わせる可能性がありますので注意しましょう。寝付きが悪くて困っている方は、寝る前にテレビやスマホなどの明るい画面を見ることを控えるようにしましょう。
「色々と気をつけたけれどどうしても眠れなくて困っている。なんとかしたい!」という方は新しいタイプの睡眠薬を試してみるという選択肢もあります。
最近、従来の睡眠薬(ベンゾジアゼピン系)とは異なるタイプの睡眠薬が開発されました。それは上記のメラトニンというホルモンの作用を増強して眠気を誘うという薬剤です。ベンゾジアゼピン系のように脳全体を鎮静化して眠くなるのではなく、より自然な睡眠を促すと言われています。現在、日本で市販されているのは「ロゼレム」という薬剤で、メラトニンのアゴニスト(本物と同じ効果がある偽の物質)です。海外ではメラトニン自体がサプリメントとして売られているようですが、日本では入手困難です。また、「ベルソムラ」と「デエビゴ」という薬剤もあり、こちらは「起きようとする」覚醒系に作用するオレキシンという物質をブロックする作用があります。こちらも、従来の睡眠薬と比較して自然な睡眠を促す効果があります。
30代の男性で、不眠症で色々と睡眠薬を飲んでいるが、よく眠れないという方がいました。その方がロゼレムを使用したところ、徐々によく眠れるようになり、最後には薬を飲まなくても大丈夫になりました。体内の睡眠に関する神経中枢やホルモンのサイクルが、正常に戻ったのだと思われます。効果には個人差があるでしょうが、人によってはとても有効な薬剤のようです。



