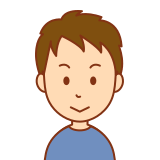
いつも飲んでいた薬が、聞いたことのない製薬会社の薬に変わったんだけど、どうしてわざわざ変えるんだろうか?

ジェニリック薬といって、値段が安いものに変わったのでしょう。変える理由は患者さんの負担軽減もありますが、実はもっと大きな原因があります。
増大していく一方の医療費。これをできるだけ抑制しようと、厚生労働省はジェネリック薬の使用を強力に勧めてきました。はたして、医療費は抑制されたのでしょうか。
高血圧の治療が始まると処方される内服薬。最近はジェネリック医薬品というものが増えてきました。このジェネリック医薬品は後発品などとも呼ばれますが、一体どういった薬なのでしょうか。
私が医師になりたての20年ほど前にも後発品は存在していました。その頃はジェネリックなどという格好良い呼び方はせず、「後発品」とか「ゾロ」などと呼ばれていました。なんとなくB級品のような感じの扱いで、私の周りでは積極的に使おうとする医師はあまり見かけませんでした。潮目が変わったのは、厚生労働省が医療費削減のためにジェネリック薬の使用を強く励行するようになってからです。初めのうちは「医師の裁量で…」という感じでしたが、徐々にノルマを作ってプレッシャーをかけるようになっていきました。初めのうちは半信半疑で使用を始めたジェネリック薬でしたが、その割合が増えるに従って医師たちも抵抗を感じなくなってきているようです。しかし、使い始めた頃は
・薬理作用は本当に変わらないのか
・副作用が多いということはないのか
という懸念がありました。ですが、その後も大きな問題が起こることもなく、最近ではかなりの割合でジェネリック薬を処方しています。同じ患者さんで、先発品(元々の大手製薬メーカーが販売していた薬)からジェネリック薬に変えたら、「病状が目に見えて悪くなった」とか、「急に副作用が発生した」といった経験は個人的にありません。増大していく一方の医療費をできるだけ抑制する事がジュネリック普及の目的ですが、ある程度は上手く行っているように思われます。現場の医師も、以前よりも医療コストについて意識する機会が増えてきたと思います。
ところで、一見すると良い事ずくめのジェネリック薬の普及ですが、負の側面がないわけではありません。一つは日本の製薬会社の体力低下です。ジェネリック薬がどうして安いかというと、開発のコストが掛かっていないからです。特許が切れた成分なので、製造コストだけで済むということです。一方で、新しい薬品を開発するために、製薬会社は多大な研究費を必要とします。その研究費用を回収するため、先発品の価格には開発コストが含まれていた訳です。薬の特許は基本的に10年で、それを過ぎると特許は開放されます。新薬を開発する製薬会社は10年以内に開発費用を回収しないと利益が出ず、下手をすると赤字になってしまうのです。そのためか、最近の新薬は薬価が軒並み高くなっているように思われます。例えば、心房細動のある人が脳梗塞になることを予防するため、抗凝固薬というジャンルの薬を使うことがあります。以前はワーファリンという薬を使用しており、薬価は数十円の安い物でした。その後、新しいタイプの抗凝固薬が登場しました。とても良い薬なのですが、薬価は一日500円以上になります。一ヶ月で約15,000円です。心房細動の患者さんは増えて来ているので、新しい抗凝固薬を服用している方は増えていく一方です。さらには、心不全の治療薬で1日2,000円するような薬もあります。これは一例に過ぎず、他にも驚くほど価格の高い新薬が次々に登場しているのが日本の医療現場です。医療費削減のためにジェネリック薬の普及をする一方で、高価な新薬が次々と登場しているという訳です。
ジェネリック薬の普及は時代の流れのなかで必要な事であったと思います。一方で、製薬会社は生き残りのために高価な新薬を開発し続けています。これからどうなっていくのか… 良い薬を安く提供できるようになると理想的なのですがね。



